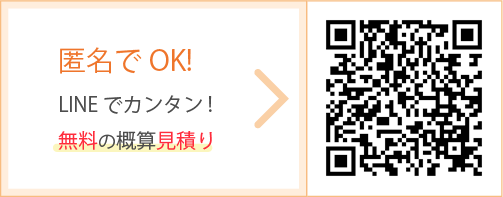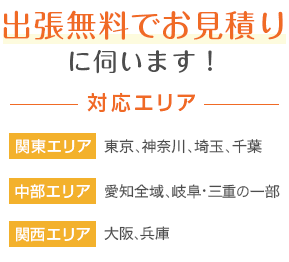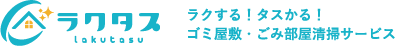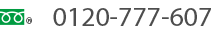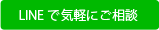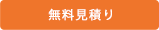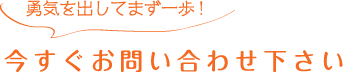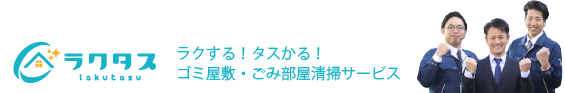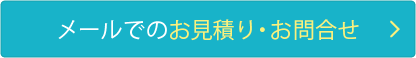更新日:2024年8月9日

古くなった畳の処分にお悩みではありませんか?
サイズが大きく簡単には持ち運べないため、どうやって捨てるべきなのか、悩むことも多いでしょう。
この記事では、畳の処分方法や注意点、処分費用について解説します。
処分する枚数や汚れの状態に加え、費用や効率性など重視したい点によっておすすめの処分方法が異なるため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
ぜひ参考にしてください!
目次
畳は何ごみ?

畳は、吸湿性の高さやリラックス効果などの特性から、古くから日本で広く親しまれている伝統文化の一つとされています。
一般的には、畳の処分の区分は、「燃えるごみ」または「粗大ごみ」として扱うことが多いです。
また、畳の構造や芯材によって分別が異なることもあります。
ここでは、畳の種類や寿命について詳しく解説します。
畳の種類・素材
畳は、畳床(芯材)と畳表(表面のい草)から構成されており、畳床を畳表で包んで作られます。
畳床の種類は主に下記の3通りです。
- 藁床(わらどこ):稲わらを使用した畳床で、弾力性に優れる。
- ワラサンドイッチ床:ポリスチレンフォームなどの合成材料を使用し、ダニの繁殖を抑える効果がある。
- 建材床:木製の繊維やポリスチレンフォームを主な材料とし、湿気の影響を受けにくい。
畳表の素材は、「い草」「和紙」「樹脂」の3種類が代表的です。
- い草:吸湿性・消臭効果がある。色が変色しやすく、耐久性が低い。
- 和紙:樹脂コーティングで耐久性に優れ、カビやダニに強い。バリエーションが豊富。
- 樹脂:ポリプロピレンを使用し、耐水性がある。掃除がしやすく、摩擦に強い。
畳は、素材によって耐久性、メンテナンスのしやすさが異なります。
天然素材ならではの色の変化を楽しみたい場合は「い草」、頻繁に出入りする場所には「和紙」や「樹脂」が適しています。
畳の寿命と張り替えのサイン
畳を処分する目安は、約10~15年といわれています。
張り替えを検討するサインは下記の通りです。
- 畳の色褪せ、汚れが目立つ
- 表面がささくれ立ち、繊維くずが付く
- カビ臭い匂いがする
畳が傷む主な原因には、直射日光に長時間さらされることや掃除をしていないことが挙げられます。
特に、畳の上にカーペットやござを敷いている場合、ほこりが溜まってダニやカビの発生リスクを高めてしまうので注意しましょう。
通気性も悪くなるため、定期的に掃除を行うことが大切です。
畳を長持ちさせる方法
畳を長持ちさせるには、定期的なメンテナンスが不可欠です。
「裏返し」は使用してから約5年後、その後は3~5年ごとに行い、「表替え」は裏返しから3~4年後に行います。
畳床が劣化した場合は、新しい畳への張り替えが必要になります。
日常のメンテナンスとしては、下記に注意しましょう。
- 週に2~3回は、掃除機やほうきでごみを取り除く
- 畳の上で重いものを引きずらない
- 半年に一度、日陰で畳を干して湿気対策をする
日頃のお手入れを心がけることで、きれいな畳を維持できます。
畳の裏返しや表替えは、畳の使用環境や状態に応じて、適宜行うことが必要です。
畳の処分方法は6通り!おすすめの捨て方
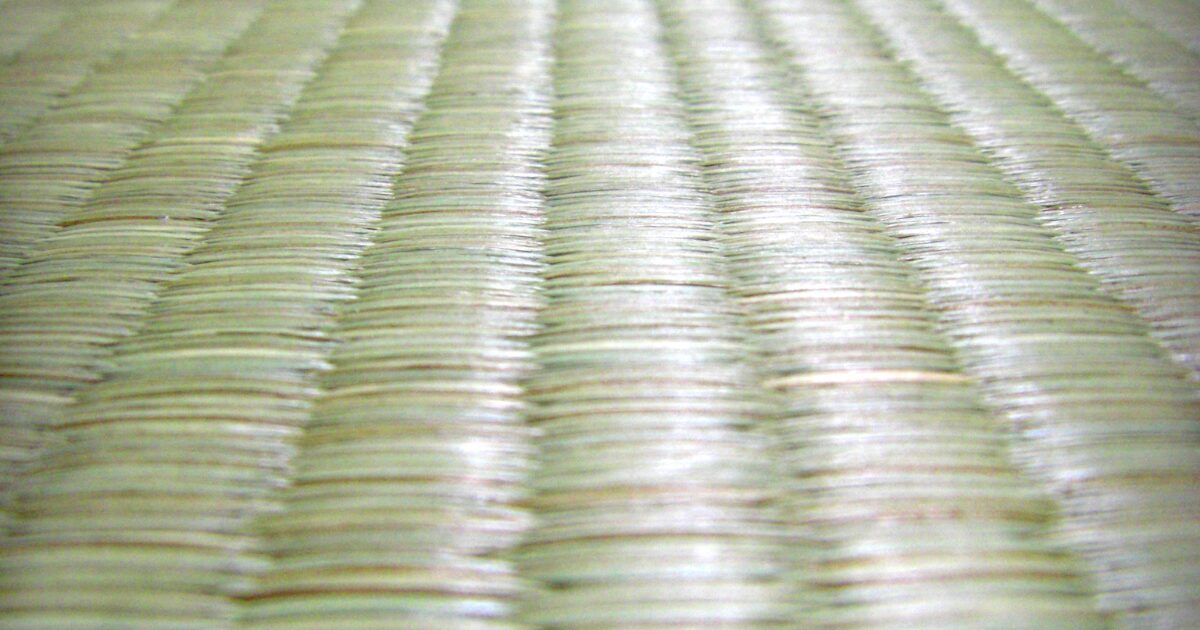
畳の処分方法は次の6通りです。
- 自治体で燃えるごみとして処分する
- 粗大ごみとして回収を依頼する
- ごみ処理施設に直接持ち込む
- 畳専門店に引き取ってもらう
- 地域の掲示板で譲る
- 不用品回収業者に依頼する
それぞれの方法を詳しく解説していきます。
①自治体で燃えるごみとして処分する
畳は、自治体で「燃えるごみ」として処分できます。
自治体が指定するごみ袋に入る大きさにカットして、袋に入れて出すことが一般的です。
自治体によって下記のようなルールが提示されているため、事前に確認してから準備しましょう。
- 収集日の朝、午前8時までに出す
- 90リットル以下の蓋つき容器、または半透明のごみ袋に入れる
- 段ボールに入れて捨てない
- 1回の排出量は、45リットル袋で3袋までとする
- 一辺90センチメートル未満に小さくする
処分費用は無料であり、少ない枚数の畳を処分したい人に向いています。
畳の取り外し方
畳の取り外し作業は、適切な道具と正しい手順を知っていれば自分で行うことができます。
必要なものは、マイナスドライバーまたは手鉤と防護用のゴム手袋やマスクです。以下の手順に沿って行います。
- 動きやすい服に着替え、手袋・マスクを装着する
- 畳と畳の隙間を探す
- マイナスドライバーを押し込む
- ゆっくりと畳を持ち上げる
畳は1枚あたり約10~30㎏と非常に重いです。
一人で無理をすると腰を痛める原因になるため、複数人で協力しながら行うことをおすすめします。
畳の解体方法
畳を解体して燃えるごみとして処分する手順は下記の通りです。
電動ノコギリまたは丸ノコを使用して、細心の注意を払いながら作業を進めていきます。
- 準備する道具:電動ノコギリ(丸ノコ)、台座、マーカー、ゴーグル、手袋
- 畳の中心をマーキング:畳を台座に置き、畳の長さのセンターに印をつける
- 台座(馬)の設置:畳を馬に乗せ、山なりになるようにする
- 丸ノコのセッティング:丸ノコの刃の長さを畳の厚みの約半分に設定する
- 切断:センターラインに沿って、畳の表側を切る
- 畳を裏返し:畳を裏返して、残りの部分を切る
畳の裏側は、しつけ糸が電動ノコギリに絡まりやすいので、慎重に作業してください。不慣れな場合は、ケガのリスクがあるため、他の処分方法を検討しましょう。
②粗大ごみとして回収を依頼する
畳の処分は、粗大ごみとしての回収依頼が一般的な方法です。自治体ごとに異なる処理手数料がかかり、事前申込みを行わなければなりません。
各市町村の処理手数料は、ホームページや電話で確認することができます。
- 名古屋市:1,000円
- 新潟市:500円
- 横浜市:1,000円
- 葛飾区:1,300円(一畳)、300円(軽量・ウレタンのみ)
- 浦安市:1,040円(15~25㎏未満)、1,560円(25~35㎏未満)
自治体によっては一度に捨てられる量に制限があったり、回収日が指定されたりすることもあります。
粗大ごみの申し込み手順
粗大ごみの受付から回収までの流れは下記の通りです。
- Web・電話で粗大ごみ受付センターへ連絡
- 粗大ごみ処理手数料券(シール)をコンビニ等で購入
- 日付や受付番号を記入し、畳にシールを貼る
- 回収日時に、指定の場所まで持ち運ぶ
マンションなど集合住宅に住んでいる方は、玄関の前に畳を排出することはできません。管理人や自治体の指定する場所を調べて、排出しましょう。
一戸建ての場合、敷地内の道路に面した場所まで運ぶことでスムーズに回収してくれます。
③ごみ処理施設に直接持ち込む
処分する畳の枚数が多い場合、ごみ処理施設まで持ち込んで処分する方法もあります。
ごみの総重量で料金が算出されることが多いです。
- 名古屋市:200円(10㎏毎)
- 東松山市:40㎏まで無料、25円(10㎏毎)
- 浦安市:220円(10㎏毎)
- 伊勢崎市:120円(10㎏毎)
粗大ごみ手数料を支払うよりも安い費用で捨てることができますが、車での荷下ろしや手続きなど労力はかかる点がデメリットです。
ごみ処理施設への持ち込み手順
ごみ処理施設に持ち込む際の受付から処分までの流れは下記の通りです。
- 畳を車に積む
- 住んでいる地域の事業所で受付をする
- 処理施設まで搬入
- 自分で荷下ろしする
- 手数料を支払う
受付時間は9時から12時、13時から16時までとなっており、日曜や祝日、年末年始は持ち込みできないのが一般的です。
混雑時には、ごみ処理施設で数時間待つこともあるため、余裕を持ったスケジュールで受付することをおすすめします。
軽トラックや自家用車がない場合は、レンタル料金も必要となるため、一概にお得とは言い切れません。
他の処分方法と十分に比較検討することが大切です。
④畳専門店に引き取ってもらう
畳専門店に引き取りを依頼することも可能です。
新しい畳へ買い替えを検討している場合はスムーズに処分できます。畳屋さんによっては撤去作業から運搬、新しい畳の張り替え作業まで一貫して任せられます。畳の引き取りを依頼する手順は下記の通りです。
- 畳を購入する専門店に、古い畳の回収が可能か確認する
- 指定された方法で料金を支払う
- 回収当日までに畳周辺や通路を整理整頓する
回収費用は畳1枚あたり約1,500~3,000円となりますが、店舗によって金額が異なるため詳細は直接問い合わせましょう。
下取りサービスがあれば、畳をお得に購入できる場合もあります。
畳のリサイクル業者へ依頼する方法もある
新しい畳を購入しない場合でも、畳を回収してくれる専門店や業者に依頼してリサイクルすることも一つの選択肢です。
回収された畳は、肥料や燃料に再資源化されます。また、伊藤畳店のような畳専門リサイクル業者なら、古い畳を炭化処理して「リユース畳」として再利用するため環境にも優しい処分方法です。
畳の状態によっては引き取れないケースもあるため、条件を事前に確認しましょう。
⑤地域の掲示板を活用して譲る
状態の良い畳なら、必要としている人に譲ることでお得に手放せます。
地域の掲示板「ジモティー」なら直接手渡しができるため、大きな畳や家具なども比較的簡単に処分することが可能です。
実際に、ジモティーでは下記のような畳が取引されていました。
- ユニット畳4枚:6,999円
- ござ(い草):0~2,400円
- 琉球畳(置き畳)9枚:6,000円
ユニット畳は床に直接置くだけで気軽に和の雰囲気を感じられるため、模様替えをしたい人に需要があります。
ジモティーであれば不用になった畳を現金化することも可能です。0円から出品できるため「早く処分したい」という方にもおすすめです。
ジモティーでの出品、引き渡しの手順
地元の掲示板「ジモティー」を活用して畳を処分する手順は下記の通りです。
- ジモティーに無料会員登録をする
- 出品ページで畳の詳細を記載する
- 写真を撮影する
- 価格設定をして投稿する
- 希望者とやり取りして、受け渡し日時を決める
- 直接手渡しをする
注意点として、畳の取り外しから搬出・荷下ろしまで全て自分で行う必要があります。大きな畳を扱う際には、作業をスムーズに進めるためにも、家族や友人の協力を得ることが重要です。
⑥不用品回収業者に依頼する
畳の処分に手間をかけたくない場合、不用品回収業者に依頼する方法もあります。
費用は、事前に見積もりが必要となりますが、1点あたり約3,000円~が相場です。
メリット①大量の畳を一度に処分できる
不用品回収業者に依頼すれば、畳1枚から数十枚まで一気に捨てられるというメリットがあります。
トラック一杯に積めるだけ積んで一定の料金で処理できる「トラック積み放題プラン」を使えば、多くの畳を捨てるほどコスパも良いです。
粗大ゴミとして1枚ずつ処分する手間も省けるため、大量に畳を処分したい場合におすすめです。
メリット②畳の取り外しから運搬までお願いできる
不用品回収業者に依頼することで、畳の取り外しから運搬まで全て丸投げできます。1枚あたり10㎏以上の重さがある畳を、自分で取り扱うのは非常に大変です。
畳を解体したり運んだりする必要がなく、体への負担を避けられるのは大きなメリットといえます。電話1本で簡単に手配できるため、時間もかからず便利です。
メリット③他の不用品も回収してもらえる
不用品回収業者を利用すれば、畳だけでなく家の中のさまざまな不用品をまとめて処分できます。
- 使わなくなった衣類
- 衣装ケース
- 書類
- 人形、おもちゃ
- 布団セット
など、押入れに眠っているものを一気に処分したい場合に適しています。
自分の都合の良い日時に回収に来てくれて、一つずつ分別する作業もいらないので、楽に家の中をすっきりさせたい時にぴったりの解決策といえるでしょう。
畳の処分費用の相場、メリット・デメリットを比較!

ここまで畳の処分方法について紹介しました。
下記を参考にしていただき、処分費用やメリット・デメリットを比較検討してください。
| 処分方法 | 処分費用の相場 | メリット | デメリット |
| 燃えるごみ | 無料 | 処分費用がかからない | 解体・運搬の手間がある |
| 粗大ごみ | 300~1,560円 | 処分費用が安い | ・手続きが必要 ・自分で運搬する必要がある |
| ごみ処理施設に持ち込む | 無料~220円 | 処分費用が安い | ・手続きが必要 ・時間に制限がある ・自分で荷下ろしする必要がある |
| 畳専門店に引き取ってもらう | 1,500~3,000円 | 買い替えの場合、下取りで安くなるところがある | 対応している店舗が少ない |
| ジモティー等で譲る | 無料 | 臨時収入が得られる | ・車が必要 ・出品作業の手間がかかる |
| 不用品回収業者 | 3,000円~ ※見積もりが必要 |
・複数の畳を一気に処分できる ・畳の取り外しや運搬もおまかせできる ・指定日時に回収にきてくれる ・畳以外の不用品回収も依頼できる |
費用がかかる |
畳の処分に関する注意点

畳の処分を行う前に知っておきたい注意点を紹介します。
リフォームで捨てる畳は自治体で処分できない場合も
リフォーム時に出た畳は、自治体では処分できないことがあります。
横浜市では、リフォーム業者による工事で出た畳は、その業者に処理を依頼しなければなりません。
リフォームを依頼する際は、畳の処分費用が工事費に含まれているかを確認しましょう。一般的に撤去費用は工事費に含まれていますが、念のため見積もり段階で確認することをおすすめします。
濡れた畳は自力での運び出しが難しい
濡れた畳の処分する際は、いくつか注意すべき点があります。
まず、水を含んだ畳は重たくなるため、運び出しが非常に困難になります。また、全ての自治体が濡れた畳を受け入れているわけではないので、事前に確認しなければなりません。
特に台風や津波などで濡れた畳は、「災害ごみ」として扱われ、家庭ごみとして処分できなくなります。放置していると、畳内部で微生物が増殖し、自然発火することも。
汚れがひどい畳は、不用品回収業者に依頼することを検討しましょう。
畳は買い取りが難しい
畳の処分において、リサイクルや再販に対応している業者は非常に少ないです。
畳は消耗品であり、一度使用されて状態が悪くなったものはほとんど需要がありません。
また、畳のサイズは部屋に応じてカスタマイズされることが多く、地域差もあるため、買い取りができないのです。
リサイクルによる再利用の取り組みはあるものの、多くの場合、畳は廃棄されるのが現実です。
畳の処分はラクタスにおまかせください!

畳の処分方法は、下記の6通りです。
- 自治体で燃えるごみとして処分する
- 粗大ごみとして回収を依頼する
- ごみ処理施設に直接持ち込む
- 畳専門店に引き取ってもらう
- 地域の掲示板で譲る
- 不用品回収業者に依頼する
古い畳の処分方法は複数の選択肢がありますが、畳の状態、処分する枚数、費用の面などを総合的に考慮することが重要です。
ごみ処理センターへの持ち込みや地域の掲示板を利用する際は、車の用意が必要となるだけでなく、取り外しや運搬も自力で行う必要があることも把握しておきましょう。
面倒な作業なく、すぐに処分したい場合は不用品回収業者に見積もりを依頼することをおすすめします。
愛知県名古屋市に拠点を持つ不用品回収業者「ラクタス」では、畳の状態に関わらず最短当日で回収に伺うことが可能です。夜間や早朝など、お客様のご都合に合わせて対応しておりますので、手間なく処分できます。
また、ハウスクリーニングや引っ越しごみの処分、空き家の整理などのサービスも提供していますので、お気軽にご相談ください!